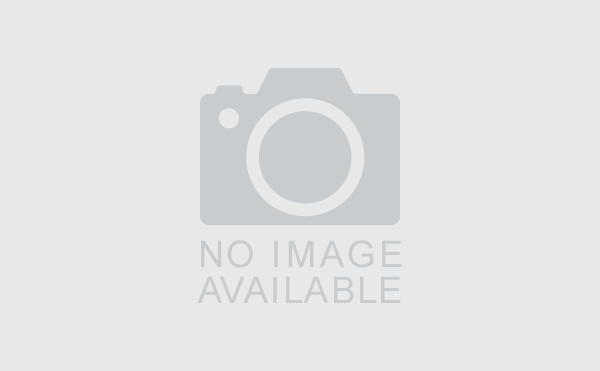当たり前の差
当たり前の差
熊高 済々黌 高専 第一 第二を目指す方へ
熊高 済々黌 第一 第二 高専 合格力育成の専門の少人数定員制の明成塾です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
学力アップは、家庭で培われた子供にとっての「当たり前」が何かによる。
当塾の小学生の塾生には、他の塾の経験者が少なくない。彼らの面白い点は、共通して同じ問いかけをする点である。「先生、宿題は何ですか。」これは、中学生で転塾してきた生徒さんにも言える。学校も宿題をさせて、それをチェックするという工程が相変わらずあると聞く。生徒は、なにやら「自学ノート」といったものに、勉強の痕跡を残して担任に見せるようだ(学校によってはない学校もある)。この種の作業がダメだとは言わないが、そもそも勉強が誰のためのものかという点が抜けている。自分のためにやるべきことをやればいいだけの話である。いやいやながら、親から言われて日々プリントに解答するようなお子さんもいると聞く。たしかに、勉強しない子にとっては、親としてそうするしかないようにも思えるが、そのような子であっても自分の意志で取り組むことの大切さを小学生のうちに感じとらせるべきだと思う。そうでないと、勉強=命じられたことをやるという形式に陥ってしまうからである。
中学生では、テストで学年順位がでるが、150名の中学なら、実は50位も20位もあまりかわらない。入塾後に学年60位あたりから学年20位程度に上がったりする。ここでのポイントは、行動力。そもそも中学での勉強は、小学卒業時点で標準的な学力がある生徒さんの場合には、反復して知識を身に着ける行動力があるかどうかで決まる。おもしろいもので、この行動力のないお子さんを、形式的に「山ほどの宿題」を与えてくれるタイプの塾が待っている。そのような塾に長年通ってみて、どうも学力が上がらないと言ってみたり、その保護者の方が、「長く通ったんですが成績が上がりません」と言って相談時に話されることがある。実はそのような場合の本質は、上がるような行動をとっていないことがほとんどと言っていい。本気で日々できない箇所や苦手な箇所を見つけては、できるようにしているのか。次の試験のために日々計画的に進めているのか。このような「当たり前」のことが、その生徒さんにとって当たり前になっているのか。
今は、4月下旬であるが、中学によっては6月10日ごろに定期テストがある。また7月の初めに定期テストがある中学も少なくない。前者の場合には、少なくとも試験範囲を5月の中頃までには終わらせること。後者の場合には6月の中頃までには終わらせることが、学力を大幅に伸ばすことにつながる。このようなことを意識して勉強しているかどうか。特に新中1は挽回の数少ない機会である。
ご参考
これまでの塾生の在籍中学)明成塾という小さな専門塾に多くの中学の生徒さんが来られています
西山中 三和中学 藤園中学 井芹中学 白川中学 城西中学 飽田中学 花陵中学 力合中学 出水中学 出水南中学 下益城城南中学 河内中学 熊大附属中学 信愛女学院中学 九州学院中学 文徳中学
学力は変えられます。ここでは、大幅に学力を伸ばすお子さんばかりです。本気で学力を伸ばしたい方は、お気軽にお問合せ下さい。
ご相談はこちら⇒明成塾(お問合わせ)
*本当に学力を伸ばしたいお子さんと出会えればと思います。なお残席のない場合はご了承ください。
最新のお知らせはこちら